1.鵞足炎とは?原因と症状を知ろう

鵞足炎とは?原因と症状を知ろう
「鵞足炎(がそくえん)」って聞いたことありますか?実はこれ、膝の内側に痛みが出るトラブルの一つなんです。とくにランニングや階段の上り下りが多い人、または膝を酷使しがちな人に起こりやすいとされています【引用元:https://lionheart-seikotsuin-musashino.com/blog/4139/】。
まず「鵞足(がそく)」って何?というところから。鵞足とは、縫工筋・薄筋・半腱様筋という3つの筋肉の腱が、すねの骨(脛骨)の内側に集まって付着している部分のことを指します。見た目がガチョウの足に似ていることから「鵞足」と呼ばれているそうです。ちょっと面白い名前ですよね。
じゃあ、どうしてそこが痛くなるの?――それは、繰り返される膝の曲げ伸ばしによって、腱と骨の間にある滑液包というクッションのような組織が炎症を起こすからと言われています。これが「鵞足炎」です。
「歩くだけでズキッとくる…」「朝の階段が地獄…」そんな声が多く、なかにはじっとしていても違和感を感じるケースもあるようです。特徴的なのは、膝のお皿よりも少し下の内側にピンポイントで痛みを感じること。触れると痛い、押すと痛い、そんなサインがあったら注意が必要かもしれません。
また、膝の使い方が偏っていたり、太もも周りの筋肉が硬くなっていたりすると、余計に鵞足部に負担がかかると言われています。たとえば「最近急に運動を始めた」とか「立ち仕事が増えた」などの環境の変化も、原因の一つとされているそうです。
ただし、痛みがあるからといってすべてが鵞足炎とは限りません。他の膝のトラブルとも似ているため、心配なときは専門家に相談してみるのが安心かと思います。
#鵞足炎
#膝の痛み
#ストレッチで予防
#内側の膝痛
#スポーツ障害
2.鵞足炎にストレッチは効果的?リスクと注意点

鵞足炎にストレッチは効果的?リスクと注意点
「鵞足炎にはストレッチがいいって聞いたんですけど、本当にやって大丈夫ですか?」
こんな質問、よくあります。実際、ストレッチは鵞足炎の予防や再発の軽減に役立つ可能性があるとされています【引用元:https://lionheart-seikotsuin-musashino.com/blog/4139/】。でも、やり方やタイミングを間違えると逆効果になることもあるので注意が必要です。
まず、ストレッチがなぜ有効だと言われているのか。鵞足炎の原因のひとつに、太ももの内側や裏側の筋肉が硬くなり、膝の内側に余計な負担がかかってしまうことがあると言われています。そのため、縫工筋・薄筋・半腱様筋などの柔軟性を高めることが、負担の軽減につながると考えられています。
ただし、ここで注意しておきたいのが「急性期」。つまり、炎症が強く出ている時期です。この時期に無理にストレッチをすると、かえって炎症が悪化してしまう可能性があると言われています。例えば、強く引っ張るようなストレッチや、痛みを我慢しながら行う動きは、逆に体を緊張させてしまうこともあるようです。
「じゃあ、どんなストレッチならいいの?」
この疑問に対しては、まずは痛みが落ち着いてから、やさしい範囲で動かすことから始めてみるといいかもしれません。たとえば、太ももの裏側(ハムストリングス)を軽く伸ばすようなストレッチは、比較的安全だと言われています。呼吸を止めずに、反動をつけないことも大切ですね。
また、ストレッチの前に温めることで、筋肉が緩みやすくなるとも言われています。お風呂上がりなどのタイミングに取り入れると、より効果的かもしれません。
ストレッチは万能ではありませんが、うまく活用すれば回復のサポートになる可能性もあります。まずは痛みの強さに合わせて、無理のない範囲から始めてみてください。
#鵞足炎ストレッチ
#ストレッチ注意点
#膝の内側の痛み
#急性期は要注意
#筋肉の柔軟性向上
3.鵞足炎におすすめのストレッチ5選【写真や図解があればベター】

4.ストレッチだけじゃない!鵞足炎を改善するための日常生活の工夫
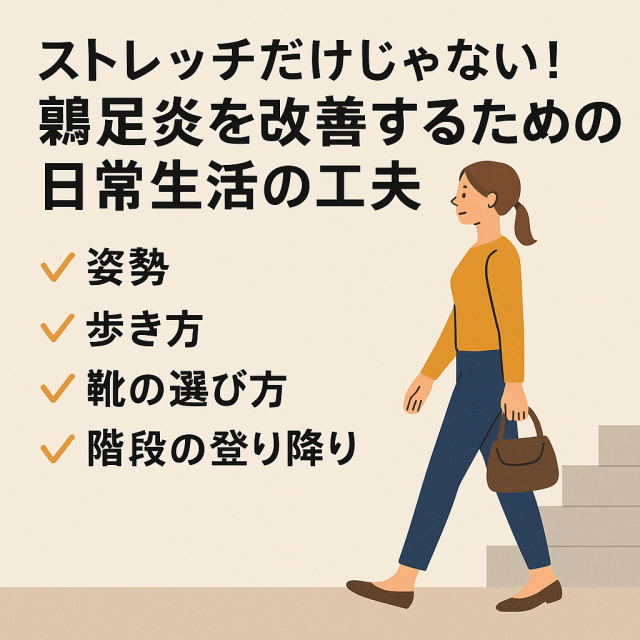
5. ストレッチで改善しないときは?受診の目安と治療法
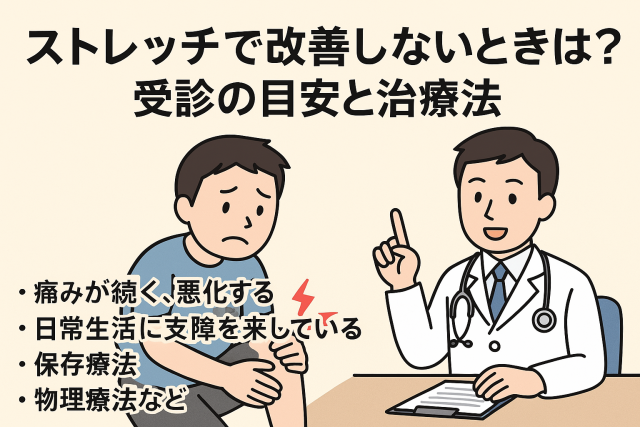
ストレッチで改善しないときは?受診の目安と治療法
「ストレッチしても、なんだか痛みが取れない…」
そんなふうに感じたことはありませんか?鵞足炎の痛みが長引いたり、逆に悪化してきたように感じたときは、我慢せずに専門家に相談することが大切だと言われています【引用元:https://lionheart-seikotsuin-musashino.com/blog/4139/】。
では、どのタイミングで来院を考えるべきなのでしょうか?ひとつの目安として、「安静にしていても痛む」「日常生活に支障が出ている」「階段の上り下りがつらい」「腫れや熱を持っている」などの症状が続く場合は、専門的な視点からの触診がすすめられるようです。
来院した場合、まず行われるのは「保存療法」と呼ばれるシンプルなケア。たとえば、炎症を抑えるためのアイシングや、痛みを避ける動作の指導などが基本になります。また、膝への負担を減らすためのサポーター使用も選択肢のひとつとされています。
さらに、痛みが慢性化しているケースでは、「物理療法」と呼ばれる施術が用いられることもあります。これには、電気刺激や超音波、マッサージ、筋膜リリースなどが含まれ、それぞれの状態に合わせた対応が行われるようです。
また、整形外科だけでなく、整体院などでも柔軟性や筋バランスの調整を目的とした施術が行われているところもあります。どちらに通うべきか迷ったときは、自分の生活スタイルや目的に合った選択をしてみるのが良いかもしれませんね。
ストレッチは予防や軽度のケアには役立つことがあるとされていますが、状態によってはそれだけでは対応が難しいことも。痛みを我慢せず、「おかしいな」と思った時点で、早めに専門家に相談することが、悪化を防ぐポイントだと考えられています。
#鵞足炎の来院タイミング
#ストレッチで治らない膝痛
#保存療法の選択肢
#物理療法の効果
#膝の痛みと整体選び









お電話ありがとうございます、
いちる整体院でございます。